
雪の北海道、旭川からやってきた。木工家具の産地、旭川の高い技術で作られた、やさしい音のする雪だるまのラトル。
おとだるま
北海道の真ん中。冬は日本で最も寒さの厳しい場所として知られる場所、旭川。上川盆地の中心部にあり、石狩川や忠別川など、大小130もの川が流れる、自然の豊かな場所。この旭川市は家具の製造でも有名で、日本の五大家具産地のひとつであり、卓越した技術力を持った家具職人の集まる街です。
この街で作られた「おとだるま」。やさしい手触りの本体を持って、耳のそばで振ってみてください。すると、カラカラと耳に心地よい音がします。
小さなお子様にもしっかり握って持てる大きさと形にしたら、こんな「雪だるま」の形になりました。目の穴から鈴の音色が聴こえてきます。山田佳一朗がデザインし、木工職人の井上寛之が1本の木から削りだしてつくりました。雪の旭川からやってきた、雪だるまの形をしたラトル「おとだるま」です。

本体に使った木材は、くるみ材とかえで材の2種類。どちらも木の風合いが良くお分かりいただけるよう、また小さなお子様にお使いいただくものですから、有機溶剤を一切使わず、自家製オイルだけで仕上げてあります。
木工ろくろを使った極めて高い技術を駆使し、きれいに、また出来る限りの安全性を配慮して作られた「おとだるま」。どこにも継ぎ目も大きな穴もないのに、さてどうやって中に鈴を入れたのでしょうか?
手にして遊ぶうちに、時間が経過してゆくほどに素材が変化して、さらに味わいが増してきます。小さな時に遊んだラトルが、そのままリビングのサイドボードや本棚に置いておく飾りになって、ずっと居てくれるように。そんなふうに考えてデザインされました。お子様の産まれたご家庭へのプレゼントにも最適です。
この「おとだるま」は、旭川市の木工職人とプロダクトデザイナーが一緒に考えて作った子供用品のプロジェクト「コド木工」のひとつとしてつくられました。
この街で作られた「おとだるま」。やさしい手触りの本体を持って、耳のそばで振ってみてください。すると、カラカラと耳に心地よい音がします。
小さなお子様にもしっかり握って持てる大きさと形にしたら、こんな「雪だるま」の形になりました。目の穴から鈴の音色が聴こえてきます。山田佳一朗がデザインし、木工職人の井上寛之が1本の木から削りだしてつくりました。雪の旭川からやってきた、雪だるまの形をしたラトル「おとだるま」です。

本体に使った木材は、くるみ材とかえで材の2種類。どちらも木の風合いが良くお分かりいただけるよう、また小さなお子様にお使いいただくものですから、有機溶剤を一切使わず、自家製オイルだけで仕上げてあります。
木工ろくろを使った極めて高い技術を駆使し、きれいに、また出来る限りの安全性を配慮して作られた「おとだるま」。どこにも継ぎ目も大きな穴もないのに、さてどうやって中に鈴を入れたのでしょうか?
手にして遊ぶうちに、時間が経過してゆくほどに素材が変化して、さらに味わいが増してきます。小さな時に遊んだラトルが、そのままリビングのサイドボードや本棚に置いておく飾りになって、ずっと居てくれるように。そんなふうに考えてデザインされました。お子様の産まれたご家庭へのプレゼントにも最適です。
この「おとだるま」は、旭川市の木工職人とプロダクトデザイナーが一緒に考えて作った子供用品のプロジェクト「コド木工」のひとつとしてつくられました。
Product Guideプロダクトガイド
天然木を使用しています。そのため木目等はひとつひとつの製品で異なっています。








Variationsバリエーション

おとだるま かえで

おとだるま くるみ
Interviewインタビュー
作り手・インタビュー 井上 寛之さんにうかがいました
旭川市に工房を構える『工房 灯のたね』の代表者。木工旋盤という加工技術を用いて、普段は「照明器具」を主に製作していますが、枠にとらわれず、様々なものづくりを行っています。

ラトルというアイテムの特性から、対象年齢はとても低く、乳児の頃から使用します。その為、安全性には特に気を使いました。
「振る」という行為だけではなく、「落とす」、「叩く」といったことも考えられ、それによって破損してしまい、内部の鈴を誤飲してしまわないように、造る側だからこそわかる情報をデザイナーの山田さんと共有し、製造方法について何度も打ち合わせを行いました。
また、塗装についても有機溶剤を一切含まない自家製のオイルで仕上げているので、お子さんが舐めても大丈夫です。親御さんが安心してお子さんに与えられるモノに仕上がりました。
Interviewインタビュー
デザイナー・インタビュー 山田佳一朗さんにうかがいました
1997年武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科 インテリアデザイン専攻 卒業。同大学研究室助手を経て2004年KAICHIDESIGNを設立。“違和感”を“共感”に変えるインテリアプロダクトをデザインしている。
ミラノサローネサテリテ(2004~2006)、デザイナーズカタログ10(2004)、A Dream Come True(ミラノ、2007)等出展多数。
この製品をつくる、きっかけとなった出来事を教えてください
息子が0歳の頃、樹脂製の円筒に持ち手が付いた一般的なラトルを頂き、使っていました。それは使っていない時は床に転がったままになり、立てておけるラトルがあるといいな、と思っていました。
またラトルは2歳になるともう使わなくなる、とても使用期間の短いものです。そのためラトルとして使わなくなっても楽しめるものにしたいと考え、オブジェとして飾って置けるかたちや素材を模索していました。
最終的な製品の形状やデザインが出来上がるまでに気をつけたことを教えてください
もともとは雪だるまの形ではなく、こけしのようなかたちをしていました。ある時、木工ろくろの作り手の井上さんに「もっとパッと見てわかりやすいかたちの方が良いのでは」とアドバイス頂き、木工ろくろで作れて、豪雪の旭川で作る意味があり、子どもが持ちやすくて、立てておきたくなるかたちで…と思いを巡らせて生まれたのが雪だるまのラトルでした。
雪だるまにしてから気をつけた点は全体のサイズと鈴の音の関係です。サイズと音の聞こえ方は密接に関係しているため、様々なサイズと中に入れる鈴の大きさを変えて何度も試しました。
また、木の厚みがあまり音を通さないため、目を穴にして音が聞こえやすいようにしました。結果、赤ちゃんが持ちやすく、耳のそばで鳴る音、ということからサイズも鈴の音も小さめになりました。
この製品で使われている素材について、エピソードはありますか?
木の素材感や井上さんの技術を活かし、一本の木を削って作ることにしました。
継ぎ目はどこにも見当たりません。鈴は一体どこから入れているのでしょうか??ヒントは雪だるまの作り方、です。
ちなみにメープルは新雪でできた雪だるま、ウォールナットは春先の泥だるまを表現しています。
AssistOnのお客様にメッセージをお願いします
自分自身、子どもが生まれて多くの子どもの道具に囲まれて暮らしています。子どもの道具は一時しか使わず、その後ぞんざいに扱ったり、散らかったおもちゃの片付けに気を煩わせたりするのは残念です。
私は道具は子どもだけのためにあるのではなく、一緒に暮らす大人にとっても、成長した子どもにとっても快適な存在であってほしい、と思います。おとだるまで子どもと一緒の暮らしを快適に過ごして頂けると嬉しいです。
Brand Nameブランド
旭川でつくる コドモといっしょの木の道具 コド木工

もしかしたら、「コドモ」と「木」は、似ているかもしれません。
どちらも硬そうでいて、実は柔らかくて傷つきやすい。 丁寧に接していれば、それなりに成長して味がでてきます。
そんなコドモと木の組み合わせをまじめに考える「コド木工」。木工の産地「旭川」の作り手と、デザイナーがいっしょになって、「ああだ、こうだ」と対話を重ね、いくつかの木の道具ができました。
見たことあるような、ないようなカタチ。そして、木の手触りと存在感。コドモといっしょの毎日の暮らしの中に、とけ込んで欲しいと思います。



Recommendationsこちらもおすすめ!

ドングリころころ、やさしい光が、ベッドサイドで眠りにつくまで、あなたを見守ってくれます。旭川の高度な木工技術とLED技術の融合。「ころころあかり」もお勧め

メープル、チェリー、ウォールナットの木の肌触りの良さと風合いを楽し新しい遊び。障子や欄間などの建具に用いられる伝統的な「組子」の技術を使って作りました。「KUMIKI」もお勧め
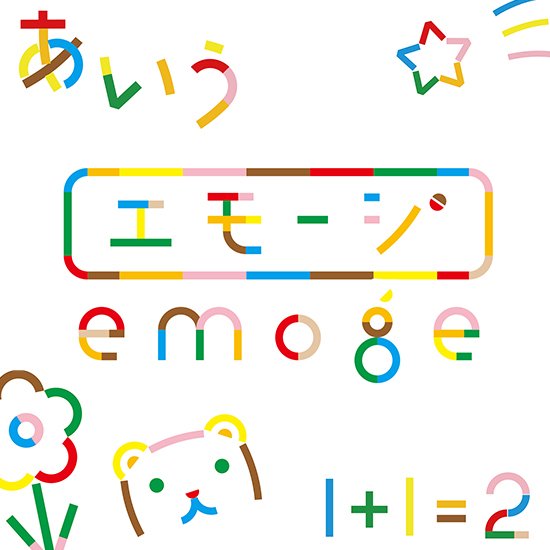
カラーフルなピースをならべて、絵や文字をつくる。子どもも大人も手を動かして気の向くまま。描くように、書くように楽しむ、それがエモージ。「emoge」